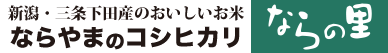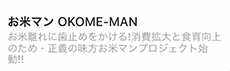10〜3月頃 田起こし・追肥・土壌作り
私達が暮らし米作りをしている新潟県三条市下田地区は、新潟県魚沼地区や福島県とは山を挟んだお隣という位置にあります。暮らすにはとても大変な豪雪地帯ですが、雪解けの水には栄養がたっぷり含まれ美味しいお米ができる隠れた米産地です。
私達の米作りは、米の収穫が終わったその時から始まります。雪解け水がたっぷりと栄養を運んでくれますがそれだけでは十分とは言えません。私達の進める「地域内循環型農業」で出来た良質な堆肥を、収穫後の田んぼに撒き「土壌作り」を行います。
秋に田んぼの水を抜いて乾かし、春に深く耕して地力を向上させます。肥料をまいてから田起こしをして土に肥料をまんべんなく混ぜ込みます。この時に有機物が鋤込まれ、微生物やミミズなどが分解して養分を作り出します。土を起こして乾かすと、土に空気がたくさん含まれ稲を植えたときに根の成長が促進されます。
4月頃 育苗
育苗はJAにお願いしています。JAでは厳選管理が行き届いていて、元気で良質な苗を提供してくれます。
4月頃 畦塗り・代掻き・田起こし
田んぼの畦が低くなっていたりするので、荒れた畦に土をすくい上げながら塗って田んぼ周りを整えます。その後、田に水を入れてかき回し、土塊を粉々に砕いてこねるようにかき回す代掻きを行います。田んぼの水もちを良くしこれから始まる田植えをしやすくする為に行います。
田植えに向け雪解け水が染み渡った田んぼをトラクターで耕し、田起こしをします。田起こしで雑草の種子が深く埋まることになり雑草の発生を減らすことが出来ます。年を追うごとに土が柔らかく深い田になり養分や水持ちが良い稲作に適した田んぼになります。
5月頃 田植え
一年で一番忙しい田植え作業を「ならやま」では組合員の共同作業で行います。作業もはかどりますし、農機具を共同所有することでコストの削減にもなります。
近年は種籾をそのまま田んぼに蒔く「直播き栽培」「ラジコンヘリを使った直播き栽培」も試験的に導入しています。
6〜9月頃 除草・追肥・育稲
稲の成長に合わせ水の量を調節します。水管理をしやすくし、有機物の分解で出てくるガスを抜き根が元気になるように溝切りをします。
この時期は雑草も元気に育ちますので、土中の栄養が雑草に取られない様に除草は欠かせません。田んぼのなかだけではなく、畦の草刈りも大切な作業です。夏の暑い時期にはとても大変な作業ですが、稲が元気に育ってくれるように願いながら行います。
新潟県下田地区は夏の日中はとても気温が上がりますが、夜には気温が下がり、稲作にはとても適した気候です。
10月頃 稲刈り・秋餅
穂が出そろってからおよそ40~45日たつと成熟期になり、黄金色の田んぼが広がります。穂の熟し具合と天候をみながら稲刈りを行います。コンバインを使って刈取り、脱穀、乾燥、籾摺りを行います。
「ならやま」の田んぼで穫れた農薬使用を最低限に抑えたお米は、隣の集落にある「新潟県畜産研究センター」の牛に飼料用米として与えられます。ならやまのお米を食べた「新潟県畜産研究センター」の牛は糞をします。その健康的な牛糞は、回収されJA堆肥センターで熟成され良質な肥料となり、「ならやま」の田んぼにまかれます。こうして「地域内循環型農業」が、本来あるべき自然の循環を取り戻し、収穫されたお米を食べる私達にはもちろん、自然にもとても優しいものとなります。
収穫を祝うお祭り「秋餅」は前日から準備に入り、当日は男性が子供達と大きな臼で餅をつきます。女性陣はつきたての餅をあんこ、きなこ、雑煮で集落の人にふるまって喜ばれています。
収穫後には田んぼに籾殻や堆肥、米ぬかなどをまいて土作りを行ったり、田んぼの水漏れや畦の壊れた場所を直したり、農機具の修理を行ったりと、来年のお米作りに備えます。

堆肥撒き作業

代掻き

元気に育った苗

田植え作業

中尾の堤

除草作業
溝きり
黄金色の田んぼ
稲刈り

秋餅
米作りのアルバム
ならやまの自然
さくら01
さくら02
さくら03
桜と鯉のぼり
椿
花いろいろ01
花いろいろ02
花いろいろ03
水仙01
花いろいろ04
花いろいろ05
花いろいろ06

とんぼ01

とんぼ02

とんぼ03

おたまじゃくし

中尾の堤

楢山川
あぜ道の野草
田植後の田んぼに夕焼け

子供が手づかみで
捕まえた『ほたる』

子供が手づかみで
捕まえた『くわがた』
楢山川のあじさい

アマガエルも

いっぱいいます。

蕎麦の花

野の花